お知らせ
ろう者学セミナー「ろう難聴児・者のレジリエンスとは:ろう者学の視点から社会を見つめる」開催報告

7月28日(日)、本学にてろう者学セミナー「ろう難聴児・者のレジリエンスとは:ろう者学の視点から社会を見つめる」を開催しました。
本セミナーは、ろう難聴児・者のレジリエンスを育み、エンパワメントを高めていくことについて理解を深めるという目的のもとで、本学と国際交流協定を結んでいる米国ギャローデット大学の教員・研究員を招いて実施したものです。当事者やろう教育・通訳関係者など多くの方々からの申し込みをいただき、対面・オンライン総計100名を超える参加をいただきました。
本セミナーの主担当である本学障害者高等教育研究支援センター講師 小林洋子氏が全体の進行を務める形で、まずセミナー前半では、ギャローデット大学 ろう者学部教授 ジニー・ガーツ氏から「オーディズム:理論的枠組みの紹介」、同大学ろう・難聴児レジリエンスセンター 翻訳チームディレクター パトリック・ブードロー氏と同センター研究員の皆川愛氏から「ろう者におけるトラウマ:レジリエントなコミュニティに向けて」のテーマでお話しいただきました。また、同大学院ソーシャルワーク研究科 准教授 高山亨太氏より「ろう者学の応用可能性:心理社会専門職を対象にした研修において〜」と題した講演をいただきました。

「オーディズム:理論的枠組みの紹介」
オーディズムとはろう者が抑圧されていることを示す概念です。ここで抑圧には言語的なものや文化的なものがあり、抑圧を行う主体も個人によるものから団体や制度によるものまで様々です。このようにオーディズムは様々な段階をもちます。このことを事例を通して確認しながら、オーディズムは理論的には3つの枠組み:「個人によるオーディズム」「制度的なオーディズム」「形而上学的(思想的)オーディズム」により分類されることが解説されました。
●「個人によるオーディズム」
ろう難聴者に対する差別を永続させる制度的偏見や先入観。
●「制度的オーディズム」
ろう難聴者に対する言明、教育の行使、住居の管理などを含む、「ろう難聴者がこういう人である」という見方に正当
を与えるもの。ろう難聴者に対する組織的な制度・慣習。(これは制度を通して永続的であり、ろう難聴者のコミュニ
ティに対する支配や権威の行使を可能にする。)
●「形而上学的オーディズム」
人間のアイデンティティや実存と言語を結び付けるものが発話であると定義されること。

現状のろう難聴者を取り巻く問題には、たとえば手話の軽視や聴覚中心の教育、身体障害者としてのろう難聴者の見方などがあります。それらは、各段階のオーディズムがろう難聴者などの当事者に集中していくことにより引き起こされているものといえます。それを解決するためにはきこえるかきこえないかを問わず「お互いに対話することが必要である」とガーツ氏は述べました。対話を通して次のようなこと:「思い込みや信念に自覚的であること」「権力とそれらが与えうる影響について認識すること」「彼等の話や自身の文化に対する解釈に耳を傾けること」「ろう文化に対する理解を深める」などが大切であることが示されました。同氏は「まず、知ろうとすることから始まる」の一文で講演を締めくくりました。
「ろう者におけるトラウマ:レジリエントなコミュニティに向けて」
本講演では「①トラウマとは」「②ろう者特有のトラウマ」「③トラウマケアの手段」の三構成でろう者とトラウマの関係について説明いただきました。

心理学におけるトラウマとは、経験したそのときだけでなく、後々の人生に影響を及ぼすほどに負荷の強い体験を指します。皆川氏は人間を卓球やテニスボールに、石をトラウマにたとえ、石がボールにぶつかったとき、卓球ボールは凹むが弾力のあるテニスボールなら一瞬凹んでから弾き返すと表現しました。ここでレジリエンスはボールの性質や凹んでも元に戻ろうとする力に相当します。
ろう難聴者におけるトラウマは、一般的なトラウマとオーディズムに起因するトラウマが二重に合わさって引き起こされる構図があります。震災・戦災や家庭におけるトラウマなど、複数の事例を確認した後にブードロー氏は「このようなトラウマにはある程度共通するパターンが見られる」と述べ、「情報・リソースの不足」「ロールモデルの不足・孤立・機会の制約」「音声の強制・ディナーテーブル症候群」などが自己肯定感の低下、アイデンティティ不全や言語剥奪などを引き起こし、ひいては長期的な問題に繋がることを指摘しました。同氏によると、アメリカでも、きこえる友達と普段一緒にいるインテグレーション児が、仕事では情報が十分に与えられず, 機会も足りないため昇給が難しいなど、このような現状がいまだ残っているといいます。
二人は「ろう・難聴児レジリエンスセンター」に所属し、トラウマケアに関する資源(リソース)を拡充するための活動を行っていますが、きこえる人のトラウマの治療に比べるとろう難聴者に対する先進的な知見はまだ多くないそうです。レジリエンスを育むために私たちにできることとして、「家族や学校など複数の場やコミュニティ内にほっとできる場所をもつこと」が大切だと最後に強調しました。
「ろう者学の応用可能性:心理社会専門職を対象にした研修において〜」
講演では一貫して「心理・社会福祉専門職が「ろう者学」を学ぶ意義とはなにか?」という問題提起を基に「専門職の状況・課題」「当事者専門職の位置づけ」「カリキュラム案」についてお話し頂きました。
心理・社会福祉専門職の例としては、ろうあ者相談員、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理士などが挙げられます。「ろうあ者相談員」は身分の不安定さ、正式な養成を受けていないなど、制度そのものに課題があります。社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理士など国家資格を要する職業においては、カリキュラムに医学モデルの考え方が強く含まれているために、ろう難聴者の抱える差別的体験の理解が難しいなど課題があります。また、ろう難聴者は情報保障や合理的配慮の課題など、養成・国家試験の段階で様々な困難に直面している現状が存在します。高山氏は、たとえろう難聴者であっても「文化言語的抑圧」や「音声情報の抑圧」のために全員がろう者学の知識を有しているわけではない旨を述べ、ろう難聴者、聴者ともに、専門職としてろう者学の知識が得られる機会が必要であると強調しました。
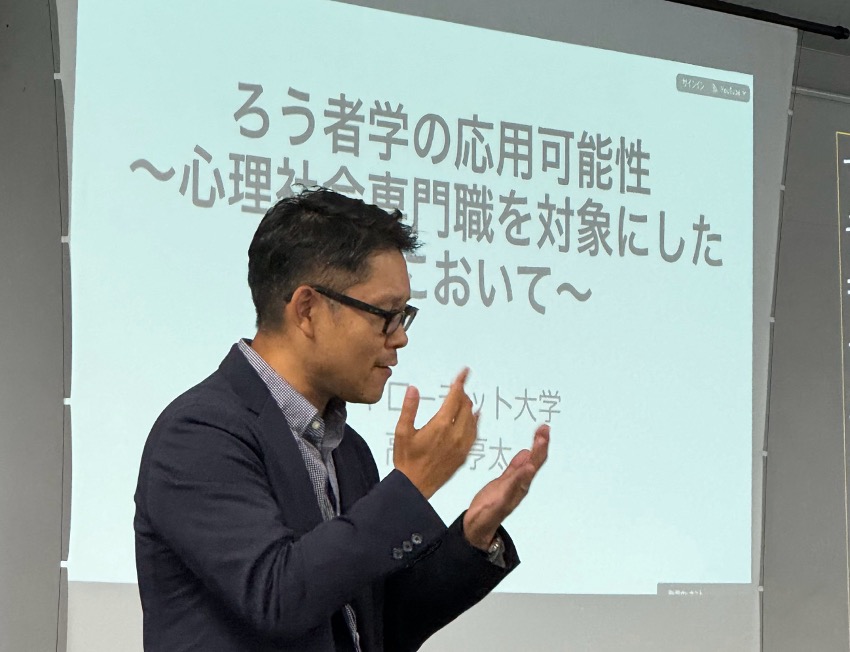
つづいてGlickman(2002)による指摘「ろう難聴者について知識のない臨床家は治療過程のなかで抑圧構造を強く生じさせることになる」を引用し、当事者が専門職に就くことは次の3点「1)ろう難聴者の内的側面や経験に対する繊細なアセスメント」「2)コミットメント形成」「3)信頼形成」を容易にするとして、その意義を強調しました。また「制度的・思想的オーディズムを打破するためにも、ろう社会内においてみずから当事者専門職を養成していく必要がある」とも述べています。
具体的な養成方法にあっては、高山氏自身が博士論文内で示した養成カリキュラム案が紹介されました。同氏はこの案に基づいたワークショップ(ろう難聴・聴者向け)を構成・実施した経験に基づき、その構成とフィードバックを講演内で詳細に共有しました。得られた知見として、ろう者学に関する日本語資料の不足や、オープンな議論の場の不足などの課題を挙げました。最後に、再びカリキュラムの開発の必要性に言及して講演を終えました。
セミナー後半のパネルディスカッションでは、本学障害者高等教育研究支援センター教授 大杉豊氏の進行のもとに、事前に寄せられた質問や主催側で用意した問題提起テーマについての議論を行いました。
まず、大杉氏による「治聾酒」の紹介より始まりました。昔から日本から言い伝えられているお酒で春分の日に飲むと"聾"が"治"るのだそうです。「これを飲もうと思いますか?」と問いかけると登壇者は、捨ててしまうか、分析にかけてしまうか......とにかく全員飲むことはないという回答でした。ディスカッションにあたっては「様々な観点が存在するなかで、このような考えを持つ人が集まった場なのだということをまず認識することが重要である」と大杉氏は述べました。

議論の内容を以下にまとめました。なお、各氏の発言は要約されています。
セミナー前に出された参加者からの質問①
「言語剥奪されたろう児がレジリエンスを育むことは可能か?」
(ブードロー氏)「言語剥奪とは、子供が成長の過程で言語を身に付けられず、そのことが人生に影響を与えている状況のこと。後から言語を身に付けようとしても、精神や活動に対する影響のために様々な事が難しくなってしまう。」
(ガーツ氏)「言語剥奪は正式には言語剥奪症候群といって、オーディズムと関わりがあることにも触れておきたい。制度的なオーディズムが浸透した結果、子供が言語を身につけられないという状況が起きてしまっている。オーディズムの医学的な見方が子供たちの言語の発達に影響を与えているところに問題がある。」
(高山氏)「精神保健の専門家として、以前東京近郊に住むろう難聴者を対象に調査を行ったことがある。日常的な困りごとを抱えたろう児は多く見られたが、病的な段階にまで至っている例はあまり見られなかった。かつて教育を受けられなかったろう高齢者がいることは事実だが、アメリカと比べると、現在の日本では深刻な言語剥奪の状況にあるろう者は少ないという印象がある。
言語剥奪を引き起こすような状況に対しては、ろう難聴児の家族や周囲への啓発活動、当事者自身がセルフアドボカシーを身に付けるための機会作りなどが重要。病的なものに対する具体的な解決策は今のところコーチングしかないと思う。成果は上がっているものの、コミュニケーションが円滑に出来るところまではいっていない。」
(皆川氏)「老人ホームで勤務していたときに70歳以上のろう高齢者と関わる機会があった。幼少期は言語剥奪がかなり行われていたはずだが、非常に生きる力が強いと感じた。それは寄宿舎があったおかげではないかと推測している。寄宿舎内でコミュニケーションがとれて、同年代の子供含め周囲との関係性があって、フィードバックが得られる、そうした環境でレジリエンスを獲得できたのではないか。」
(大杉氏)「議論が徐々にセミナーの主題に迫ってきた。無理にまとめに入らず、次の質問でより全体的な議論を行っていこうと思う。」
セミナー前に出された参加者からの質問②
「ろう児が大人に叱られたり、励ますようなコメントをもらったりしたとき、その大人がきこえているかどうかによって子供の受け止め方が異なるのではないか。とくにきこえる大人が「あなたなら出来る」と述べるとき、その根拠はどこにあるのか、それは理にかなうものなのか?」
(高山氏)「かつてカウンセリングで出会ったろうの子どものなかには、自信がもてないという子たちがいた。そこで気づいたことだが、寄宿舎があって日本手話話者のろう教員が一定数いる学校と、寄宿舎がなく日本手話話者がおらず学校を見比べたときに、前者の子どもたちのほうが、先生に対する不満を言いやすい状況が見受けられた。ゆえに、ロールモデルと寄宿舎の2点が重要なのではないか。家庭における家族との関係性も関わってくるだろう。」
(皆川氏)「私はかなり大きくなってから「ろう文化モデル」というものを初めて知った。前までは「障害者ではない、きこえる人と対等だ」と思っていたが、「ろう文化モデル」を知って考え方が変わった。ろう者はろう者の生き方がある。聴者社会やオーディズムなどから影響を受けているなかでも、当事者は色んな成功体験を積み重ねていることがもっと知られてほしい。その状況が知られないがゆえに、うまくいかないことが多いのではないか。」
(大杉氏)「(2人の答えに対して) キーワードのひとつは「信頼関係」だろう。
きこえる人に囲まれているなかでは、ろう児本人に付随する障害という部分はどうしても消えない。そんな中で、コメントをくれる大人と本人の間に信頼関係があるかどうかがとても重要になると思う。もし家庭内でそういう関係性を築くのが難しかったとしても、寄宿舎など外の場所でそういう関係を築くことが出来れば、レジリエンスを獲得しやすくなるだろう、という形で答えとさせていただく。」
セミナー前に出された参加者からの質問③
「ろうの子供のいる家族における親・祖父母の役割について教えてください。」
(皆川氏)「家がホッとできる場であること。ディナーテーブル症候群になってしまうのは、自分ひとりだけがきこえない寂しさに気づいてしまうから。子供の寂しさに気づいてあげて、家庭での役割をうまく調整していくこと。」
(ガーツ氏)「関係づくりが鍵になる。たとえたどたどしい手話でも子供のために頑張ってコミュニケーションをとろうとすれば、その努力の気持ちはきっと伝わる。それが将来的にいい方向に向かうだろう。」
(ブードロー氏)「補足だが、きこえる親のもとにろうの子供が生まれたら、みんなショックを受けるパターンが多いと思う。そのときどんな情報が回りから得られるかがその後の親子関係を決定するといっても過言ではない。
とくに子供が成長してろうコミュニティの一員になることに戸惑う親は多いが、ろうコミュニティの一員であることと、きこえる親との関係は本来両立できうるもの。そうすれば子供は家に帰ってくれば家族とコミュニケーションがとれる。ただし、そこに手話がなければ子どもは帰ってこないだろう。」
主催側が用意したテーマ①
「オーディズムは個人として、あるいはろう者コミュニティとして立ち向かえるものか?」
(大杉氏)「3つのレベルにあるオーディズムが複雑に絡み合った結果として現状のオーディズムがあり、それを無くすのは非常に難しいこと。今後個人で頑張って対応していくのか、ろうコミュニティとして団結して立ち向かうのか、という質問。
2016年アメリカ大統領選挙でヒラリー・クリントン氏が敗北した際の演説にて、「硬い「ガラスの天井」を私は破ることができなかった、しかしいつか次の世代たちの誰かが破ってくれるだろう」と話した。それと同じようなイメージがこの質問に対してある。皆が気持ちをあわせてコミットしていかないといけないだろうと考えている。」
(ガーツ氏)「1人の力では達成できないことだろう。これまで先人たちがなにかが良くない状況に陥り、それを変えていったときも、おそらく1人でなくいろんな人が力を合わせてそれを成し遂げたのだと思う。「数こそがパワーだ」というフレーズがある。先駆者となる人が火蓋をきって行動を起こしてくれたとする。すると色んな議論が生まれ、どのように運動を進めていくか意見や提案が交わされる。そうして集合知が生まれるのだと思う。」
(ブードロー氏)「これまで、ろうコミュニティは「なにかがおかしい」と思ったときにはきちんと「ノー」と言ってきた。目の前にある現状を変えるために、議論を交わし、行動を起こしていく。その先に「予防的な行動をとる」という選択肢が生まれる。
意外なことにギャローデット大学はオーディズムに対する明確な方針を、大学としては打ち出していないが、私の職場ではオーディズムに対する「ノー」は明文化されている。それを基に自分の行動原理が定まってくる、たとえば「なにかがおかしい」と思ったり不満を感じたりしたとき、明文化された「ノー」をもとにすることで、冷静にどう対処すればよいか考えることができる。明文化された「ノー」は適切な対処のための基盤になりえる。」
(高山氏)「人間という名の生物である限り、差別をなくすのは難しいだろう。だが減らすことはできる。障害者差別解消法が成立し、民間企業でも合理的配慮が義務化されたように、見える差別は今後減っていくだろうが、問題なのが見えない差別。多くの見えない差別があり、たとえば男女差別・学歴差別に加えて、日本語対応手話に対する見方の相違もあり、ろう社会のなかにもオーディズムがある。大切なことは議論を重ねることであり、そのために必要なのは教育かと思う。色々なイズムに気づき、考え、視野を広げていく機会が欠かせないように思う。」
主催側が用意したテーマ②
「レジリエンスのトレーニングシステムはどんなものが考えられるか?」
(大杉氏)「かつてろう学校は卒業後も卒業生が集まってくる、いわばろう者船の港のような場所であり、レジリエンスを身につけられる場でもあった。しかし最近はそのような役割が薄れてしまっている。ではレジリエンスをどこで身に付けるのか、皆さんの考えていることを話してほしい。」
(皆川氏)「レジリエンスを身に付けるためのトレーニングには、マイナス思考をプラス思考に変えていくようなものが実際にある。個人が自信を付けるための環境も必要になる。
また、ろう難聴者のなかには「ろう難聴者だから」「危ないから」といって何かをやらせてもらえなかった経験のある人がいる。それではネガティブな経験をする機会を失ってしまう。とくに今のろう学校は、成功させたいがために失敗の芽を摘みすぎてしまう傾向があるのではないかという気がしている。もしうまく行かなくても別な方法がとれるのだから、環境を整えすぎてしまうことには懸念を感じる。」
(ブードロー氏)「子供がどうやって経験を重ねて自信を持てるように成長するか。オーディズムがある中で子供は痛みや苦しみを抱えながら成長していく。自信が成功に繋がり、それから道が開けていく。
トラウマを抱えている人へのトレーニングシステムとしては、経験を通してトラウマの大きさがどれぐらいなのか知ることをサポートすること、つらい経験をした人に対して、「君だけじゃない」「他にも同じような経験をしている人がいる」んだということを伝えること。いっしょに頑張ろうと言ってくれるサポーターがいることがいることは大切だと思う。」
(高山氏)「よく講演の依頼を頂くが、関西圏からはオーディズムや人権に関わるテーマでお願いされることが多い。関西には部落差別の歴史があるために人権に関する教育・環境・空気が醸成されているんじゃないかと思う。「人権」をキーワードにしてきちんと考えると、おのずと適したやり方、場所がわかってくるのではないか。
また、筑波技術大学では、自分の親やルーツについて調べることで自分自身を振り返る内容の講義があると伺っている。そうしたアイデアをまとめていけば、良い考え方・やり方が出来上がってくるだろう。」
(大杉氏)「(高山氏に対して) 大学やろう協会、放課後デイサービスなど人の集まる場所での実践を通してネットワークを作る過程のなかで、レジリエンスが目に見えるようになっていくのだろうと思う。」
主催側が用意したテーマ③
「あらためて問う「ろう者学」とはどのようなものであるべきか?」
「筑波技術大学に何を期待するか?」
(ブードロー氏)「筑波技術大学へ来て、この場が米国ロチェスター工科大学のようなろう難聴者と聴者の学生が共存する場でなく、ろう難聴の学生だけの独立した場なのだと知って驚いた。この大学には、ろう難聴者同士が力を合わせて前に進むような存在になってほしいと思う。」
(ガーツ氏)「ろう者学とはろうコミュニティやろう者の歴史、言語、文化について学ぶもの。世界がどのような状況にあるか把握し、ろう難聴者の言語・アイデンティティについて理解し、ろう難聴者としての誇りを持つ。そしてろう難聴者である自分に自信を持てるようになる。そこにはデフゲイン(ろう難聴であることをプラスに捉えるといった概念)も含まれる。ろう難聴者から聴者の社会に発信し、貢献することができるようになる。そういった営みを学ぶものがろう者学である。」
(皆川氏)「筑波技術大学は、大杉先生の他にもいろんな先生や手話のできる職員がいて、卒業生が戻ってくる場所、いわばろう難聴者にとっての港である。この大学には、この30年間の経験で培ったものを聴者に還元することで、ろう難聴者も聴者もお互いに得られるものがあるようになってほしいと期待している。
そしてろう者学は、ろう社会における様々な問題や差別を個人の問題で終わらせずに、どこから起きているものなのか、システムに由来するものなのか、さらに思想にまで遡るのか、そして何を改善することで問題の解決に繋げられるか、まで考えるのを助けるメガネだと思っている。トラウマについても、トラウマに由来する行動や問題を段階にわけて遡ることで、ろう難聴者の行動や問題の根本にあるものを考え、助けるためのひとつの理論だと思っている。こちらも大切な、問題を見つめるためのメガネとして持っておくといい。」
(高山氏)「筑波技術大学には、さらに様々な議論を興してもらえるよう期待している。やはり日本で憧れとなる場所(存在)があるというのが大切で、それが筑波技術大学なのだと思う。実際、私が博士号を取ろうと思った時点での目標が大杉先生であり、大杉先生がいなかったら私はこの場にいなかっただろう。
また、筑波技術大学は障害者のための大学ということで、劣った印象や障害者という烙印・スティグマと関連付けて考える人が存在する。その状況を打破するために、障害当事者の管理職が必要だと考える。筑波技術大学はこれまで聴者が中心となって進んできた節があるゆえに、今後は障害当事者の管理職も増えていくことを期待したい。そうすればろう者学のどんなカリキュラムが必要かおのずとわかり、卒業生が教員となって帰ってき、次の世代の養成へ繋がる、そういったサイクルが産まれる。このサイクルが筑波技術大学の必要とするものであって、ろう者学と筑波技術大学は分けられるものでないと思う。」
最後に大杉氏から総括を頂きました。
(大杉氏)「最後に二つお伝えしたい。一つ目。最近「ろう者学」を筑波技術大学で実施することが、聴者からも徐々に認められるようになってきた。以前はカリキュラムに「聴覚障害」という語がずらりと並んでいたが、最近は「聴覚障害」「ろう者」「きこえない人」という用語からして整理されてきた。
「ろう者学」はまだ転換期にあり、はっきりと認められるまでには至っていないものの、就活活動を始めたろう難聴学生が、ろう難聴者である自分に自信を持って職に就く自分をアピールできることを目指すキャリア教育において、ろう者学が必要だということで聴者の先生や職員のなかからも注目されるようになってきた。私にとっても新しい発見である。ろう者学とキャリア教育をともに行うことで、より可能性を広げていく。それが筑波技術大学におけるひとつの方法なのだとわかった。
二つ目。来年4月から新学部「共生社会創成学部」が設置されることになっている。学長よりセルフアドボカシーを中心にしたいと既に表明がなされている。これを受けてついに、この大学もろう・難聴者、盲・弱視者に自己理解の力・人権意識・レジリエンスを身に付けさせ、社会へ送り出すことを明確にミッションとして掲げたのだと感じている。1987年開学から、もうすぐ40年が経とうとする今、ようやくその段階にたどり着いたのだということを皆さんと確認したい。
個人的に、定年まであと3年の今、定年までの間に「大杉だからできる」と言われていたことを他の人にもできるようにしたいというのが私自身の課題としてある。とくに自分史の講義は次のような理由から非常に気を遣って行っている:
・学生ひとりひとりにこれまでのトラウマを、しかも1対1でない場で吐きだしてもらうには十二分なアセスメントを要する。
・なぜ自分史の講義を私が担うのか、なぜこの講義が必要かをきちんと表明する。
・学生ひとりひとりとの信頼関係を築く。その場限りだから話せるということを理解し、過剰な介入はしない。
こうしたことをきちんと遂行したうえで講義を行うことは簡単なことではないが、だれかに引き継ぐことを個人的な目標に掲げている。4時間と長い時間だったが、4名の講師からわかりやすい講演を頂き、議論を通していろんなことを確認できてとても充実した時間になった。この場の準備をしていただいた関係者に感謝する。」
この他、当日のセミナー参加者との間で質疑応答も活発に行われました。
本セミナーは盛況のうちに終了しました。セミナー参加者にとっても大変有意義なものになったものと思います。
最後に、ご参加いただいた皆様、運営にご協力いただいた関係者、情報保障関係者、学生スタッフの皆様に厚く御礼申し上げます。今後も、今回のような企画を開催していきたいと考えています。




